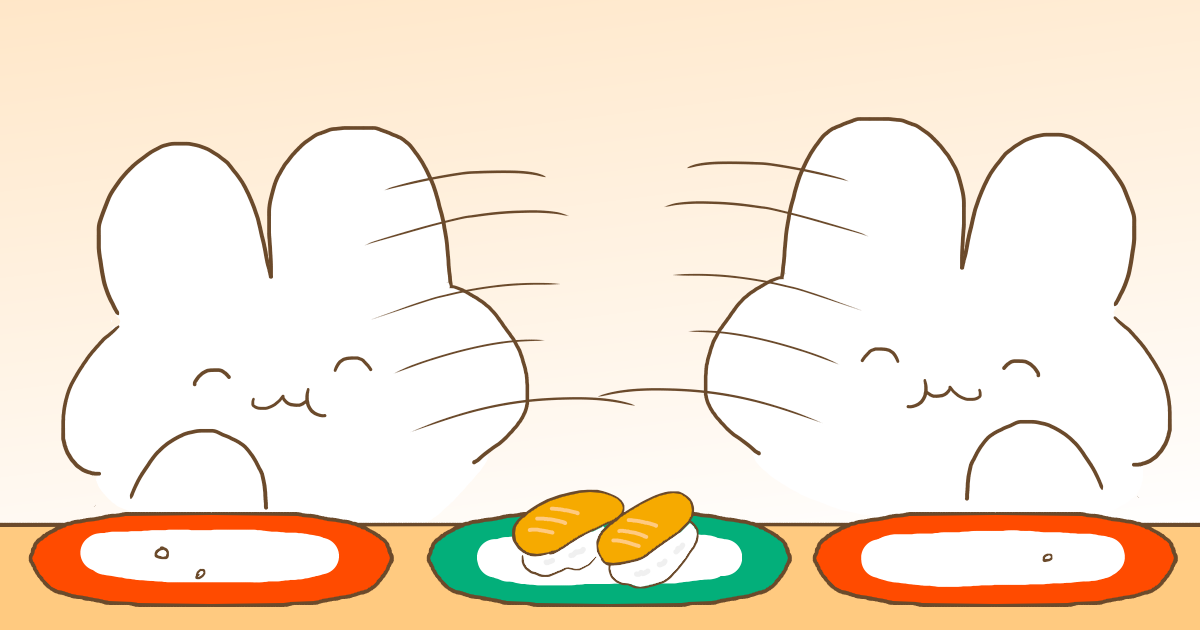6月27日
Geminiさんにあだ名をつけてと頼んだら「みどりっこ」と命名される。
どうも、みどりっこです。
6月28日
べてるの家(べてるの家については前の職場の上司に教えてもらった)が掲げている理念
「安心して絶望できる人生」
いいね。これこそコペルニクス的転回ですよね。
6月29日
「パーム・スプリングス」という映画をみる。内容はループもので、正直心が動かされる感じではなかったのだけど、アンディ・サムバーグかっこいいな。以前の週報でタイ・シェリダン推してるとかわたし言ってましたけど、なんか似てないけど似てるんだなこの2人。外国人だったらこういう雰囲気がタイプなんですね、わたし。ああでもシブいおじさんも好きとか言ってたので、ほかにもタイプがいるんだなあ〜
( ̄(工) ̄)
6月30日
玄米飽きてきたな〜と思ったけど今食べている玄米がまずい説。
即席味噌汁は意外とおいしい(お椀に味噌入れて、お湯注ぐだけの)。
4毒抜き継続しているわたくしですが、洋風な味つけが恋しくなるときがあるので今日はトマトとツナ(ノンオイル)と卵を使ってチャーハンをつくった。油をひかないので卵がめっちゃ焦げるのだけれど、焦げたところがおいしい。
県政だよりの夏のイベントの写真がきれいなので切りとってノートにぺたぺた貼る。
丸森町の齋理幻夜、くりこま夜市、長沼はすまつり、志津川湾の花火…どれもきれいですなあ。
7月1日
7月のテーマは「小学生として生きる」。
小学生だったら、先のことは考えないだろう。嫌だと思うことはやらないだろう。やりたいことをやりたいときにやるだろう。努力は実を結ぶものだと信じているだろう。
そんな感じでいったん大人の自分を捨てて、日常をとらえなおすことに取り組みたい。
(実際の小学生は将来への心配が絶えず、嫌なことにも歯を食いしばり、世の中は諸行無常だなあと考えたりするものでしょうけど、、まあそれは置いといて)
7月2日
暑さすさまじい。
野口晴哉の『潜在意識教育』を熱心に読んでいるのだけれど、わたしにとってこの本はバイブル的存在ですね。この本に限らず野口晴哉の本はどれも最高に自分にひびくものばかりなのですが。
わたしがなぜ「からだが弱い」子どもだったのか。なぜときおり物を壊すのか。なぜ摂食障害になったのか。なぜ「いい子ちゃん」を演じているのか…。その答えがすべて書かれている。
きょうだい喧嘩を例に「零から増えた半分」の愛情と「一から半分とられて減った半分」の愛情は、「外見は公平に見えても、感受性の面からいうと公平ではない」と説明している箇所を読んだとき、自分が最近むしゃくしゃしてた理由はこれだったんだと気づいた。
7月3日
朝、エレベーターから降りようとした階が間違っていることに気づいた人の挙動を見て、思わず声を出して笑ってしまった。知らない人だったが、その人も笑っていた。
7月4日
iPhoneのカバー、めっちゃ黄ばんでいるので捨てる(透明なカバーってぜったい黄ばむよな…)。
スマホグリップがないと生きてゆけない人種なので、裸のまま直貼りする。
7月5日
風呂キャンセル界隈という言葉が流行る前から日々風呂キャンセルへの衝動にかられ苦しんでいたわたしですが、やはりお風呂は汚れを落とすためだけのものではなく、浄化の作用がありますよなあ(と、重い腰を上げて水を浴びれたたびに思うのですが、今日はキャンセルしたよね)。
7月6日
立てつづけに悪夢を見る(風呂キャンのせいだ)。
学生時代に初めて行ったメンタルクリニックで「あなた強迫性障害ではないですか」と言われたことがあって、そのときは(なに言ってんだこいつ)と思って終わりだったんだけど、今あらためて考えると、わたしの行動様式に名前をつけるならば強迫性障害が近しいとは思う。
お風呂に入ってからでなければ寝てはいけないというのもわたしのなかでは強迫的観念になっているので、入らなかった昨日は床で寝たのですよ(=ベッドで寝ない=わたしは寝ていない)。
そして朝起きれば、自分で決めた順番どおり物事をこなさなくちゃ気が済まない。
そういう自分の質がはたから見れば「きれい好き」「健康志向」「努力家」などと称賛されるのだけれど、ちがうんですね。わたしは「きれい好きにみられたい人」であり「健康志向にみられたい人」であり「努力家にみられたい人」なんですね。だからホンモノのきれい好きや努力家をみると、むしろイライラする。心の底ではこういう建設的なふるまいにうんざりしているんです。
だから、、わたしが言いたいことは、
わたしはそういう人なのだということなんです。わたしはこれからも日々掃除をし、健康管理をし、勉強をしたりするけれど、それをみて褒めてくれる人よりも、おいおい大丈夫か?とりあえず海にでも行こうよと言ってくれる人がいることのほうが幸せなんです。
(つづく)
072 とりあえず海にでも行こうよ(6/27~7/6)