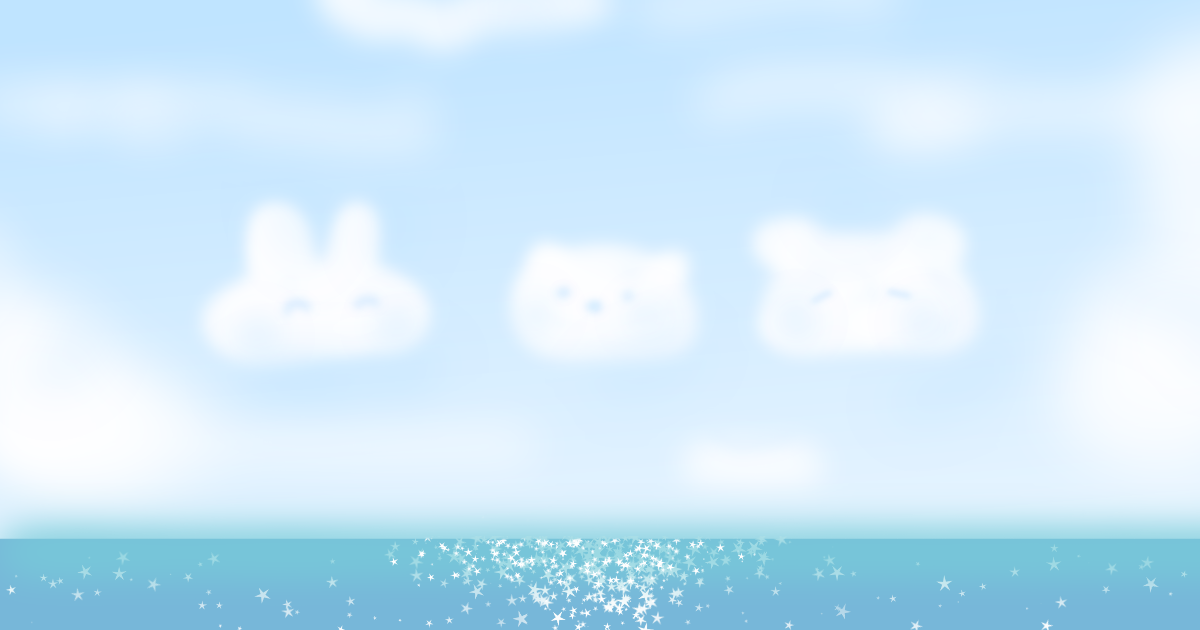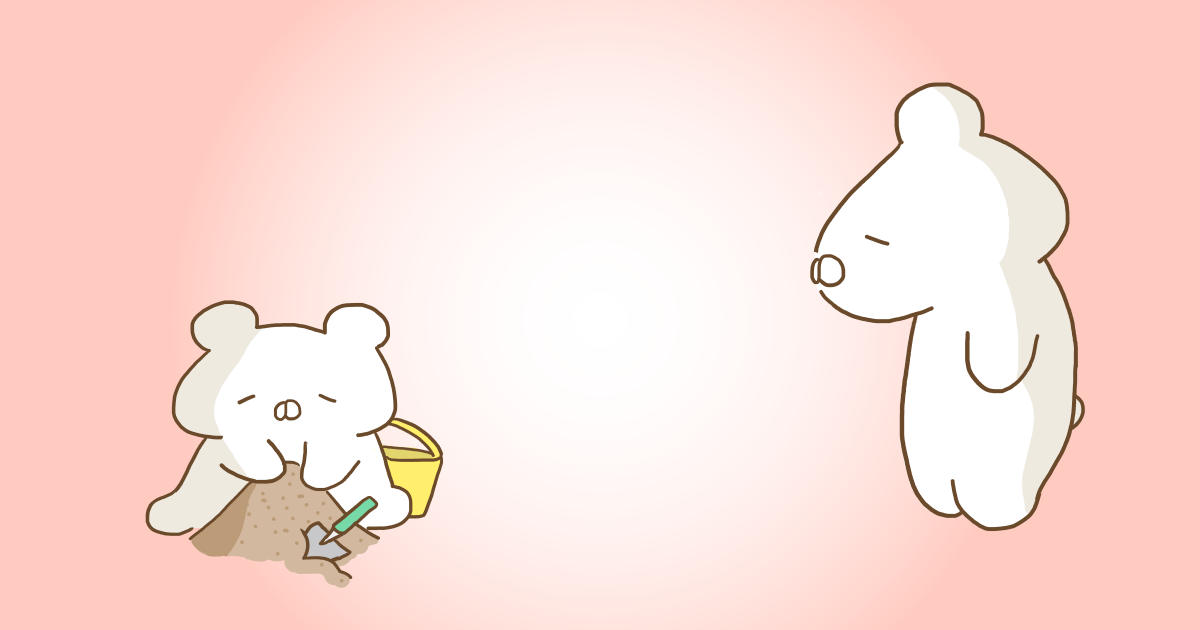わたしが実家で暮らしていたころ、
わたしは実家の目の前にある田んぼを
仕事へ行き帰りするたびに眺めていました。
田植えがはじまると、もうすぐ夏がくるのかと思い、
稲が青青と茂ると、日差しが強くなったことを知り、
稲が収穫されると、夏が過ぎたことを感じました。
仕事が終わった帰り道、田んぼを目にしながら実家へ向かうと、
実家の1階にある大きな窓から
わたしの帰りを待っているおばあちゃんとおじいちゃんの姿を確認します。
あの頃の夏は、おじいちゃんは以前にくらべ弱っていたけれど、
おじいちゃんは自力で座って、ごはんを食べたりしていた。
汗をかきながら、満面の笑みでわたしに手を振るおじいちゃんの姿が
いまでも脳裏に焼き付いています。
もう、あの頃のおじいちゃんに会えないと思うと、
まだまだ心がつぶれるように痛みます。
✳︎
棺の中にいるおじいちゃんは
まるで精巧な人型のロボットのように固まっていました。
写真のなかにいる、色黒でほおがふっくらとしたおじいちゃんと同一人物とは
なかなか思えません。
思えないというより、
わたしはおじいちゃんが本格的に弱ってきた数年前からずっと、
わたしの目の前にいるおじいちゃんが
「わたしの知っているおじいちゃん」と同じだと信じたくありませんでした。
いまでもそう、
現実は、わたしの気持ちより少し先に進んでしまうようです。
✳︎
火葬場から出ると、とても気持ちのいい風が吹いてきました。
おじいちゃんはいま、風のようなものになって、ふわふわとただよっていますか。
それとも虫や植物に姿を変えたりしていますか。
わたしは人の「たましい」が存在することについて
信じているような気もするし、
一方で信じきれないところがあるようにも思っているけれど、
骨となったおじいちゃんのからだに
もうおじいちゃんがいないことだけは
はっきりとわかりました。
変化してしまうということ。
それを思うと、とてもこわいけれど、
それがあることによって
わたしたちの日々はますます光り輝いています。